文系卒でSIerに就職しましたが、諸般の事情により2年足らずで退職しました。「文系」という立場から、SIerがツラかった理由をご紹介します。
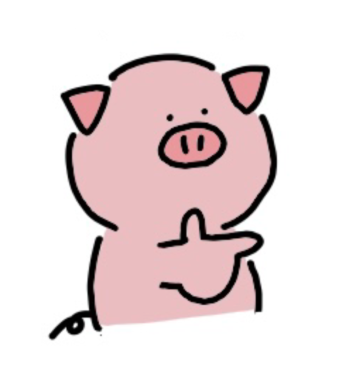
私はごはんをまともに食べられなくなるくらいしんどかった時期もありました…。これからIT業界に就職する方、転職を考えている方に少しでも参考になれば幸いです!
そもそもSIer(システムインテグレーター)の新卒って文系もいるの?

私が入社した会社の新入社員は、文系と理系が半分ずつくらいでした。理系の人がほとんどでしょ?と思うかもしれませんが、意外と文系も多いです。
SIerの新卒説明会等にいくと採用担当の方から「文系の方でも活躍されている人はたくさんいます!」と説明を受けることが多いと思いますが、苦労しながら働いている人も多くいるので注意が必要です。
文系が新卒でSIer(システムインテグレーター)に就職したら結構ツラかった理由4選!
ここからは実際に辛かった理由をご紹介します。
①「ITコンサル」という華々しいイメージとのギャップ

SIerの会社説明会では「ITコンサル」という言葉が往々にして使われます。コンサル、という言葉に惹かれて入社する場合も多いかなと思います。ですが、SIerの中で「ITコンサル」ができる部署は極わずかな場合が多いです。そりゃあコンサルする人もいれば実際にシステムを作る人も必要ですからね。
システムを作って運用する人が社員の大半なケースも稀ではありません。その会社でどのくらいの割合でどのような職種の人が働いているのかは確認するのがいいですね。
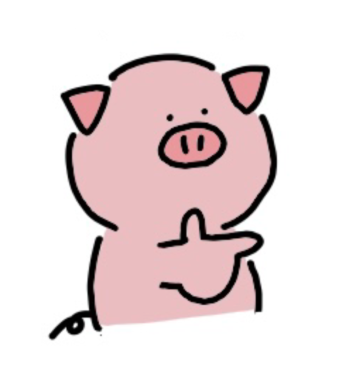
ブー谷も「ITコンサル」という職業をイメージして就職しましたが、実際に入社してみると思っていたのとは違う現実が待っていました…。
②プログラミングに関する知識・素養が足りない

SIerは「お客さんからシステム開発を受託し、実際に製作するベンダーなどを管理しながらシステムを完成させる」のが主な仕事です。いわゆる「上流工程」をメインに担当することになります。
ただ、ベンダーと会話をしたり、お客さんに説明をするときに、ある程度のプログラミング知識は必要です。そのため、新卒であればプログラミングの研修があったり、年次が低い間はSEのように開発に携わったりします。
理系卒の一部の方は大学でプログラミングを経験している一方、文系卒はほとんどがプログラミングの経験がありません。そのため、研修や仕事でプログラミングをすることになった場合、「理系の同期は開発できてるのに自分は知識すらない!!!」と悩むことになります。
③会社から取得を義務付けられる資格の勉強に時間が掛かる
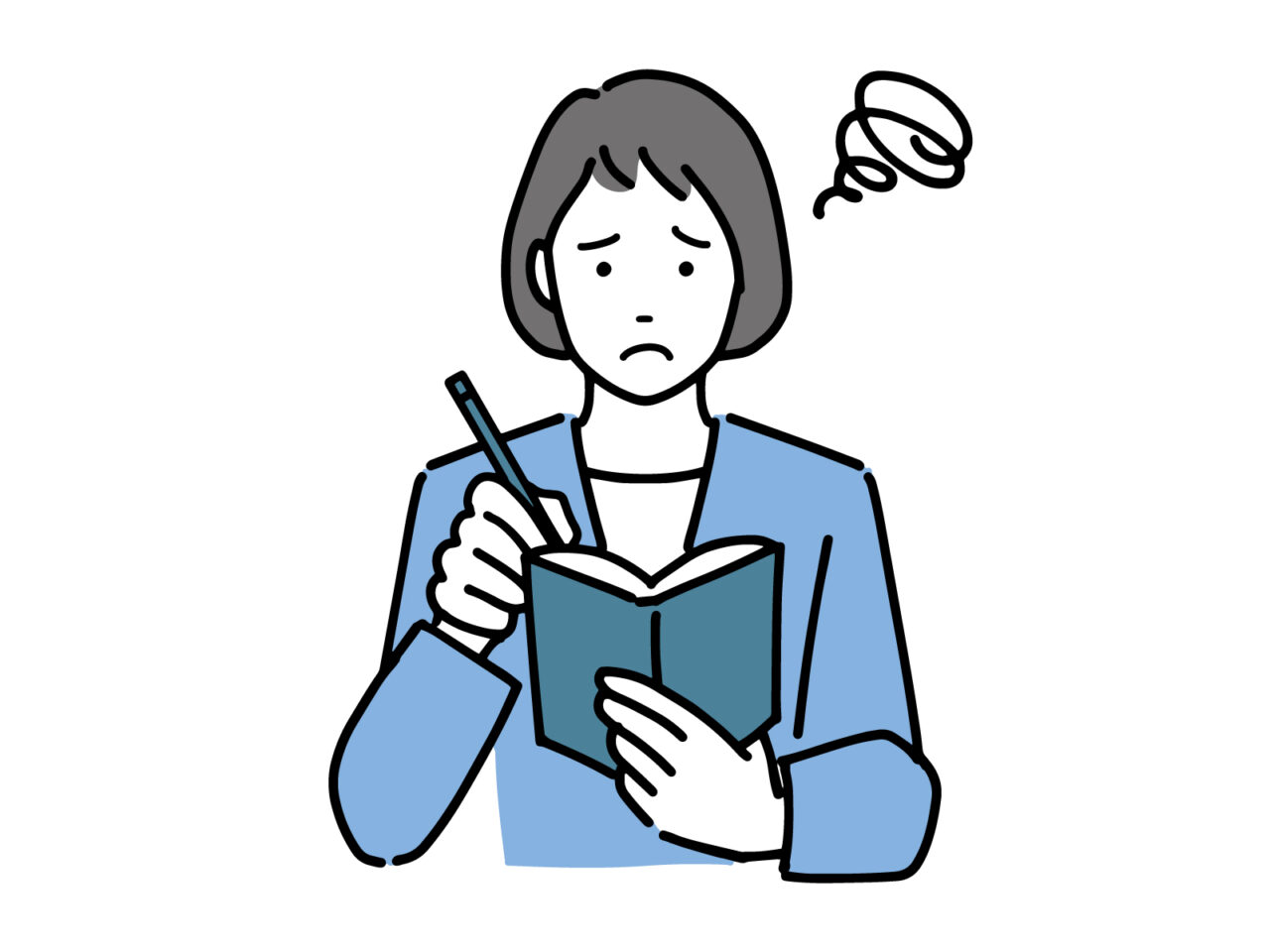
SIerでは、昇給・昇格の条件として資格の取得が必要な場合があります。例えば、情報系の資格「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」などは、さまざまな会社で取得を推奨(場合によっては義務付け)されていると思います。
これらの資格試験は、多くの問題が「理系的」な問いです。アルゴリズムの考え方や計算など、数学ができないと解くのが大変な問題が多くあります。数学アレルギーで文系を選んだ、という方にはかなり厳しい資格試験です。より上位の資格になれば、文系的な問い(論文など)もでてきますが、前提資格である下位資格につまづく可能性があります。
仕事が終わってからの時間や休日に勉強することになるので、「そんなの嫌だ!!!」という文系の方は注意が必要です。
④常にITに関する知識を学び続けなければならない

ITに関する技術は日進月歩で進化しています。クラウド・AI・コンピューターウイルス…など、良し悪しを問わず、常に新しいモノが生まれています。そのため、システム屋さんとしてやっていくなら、日々情報を取り入れ、学んでいく必要があります。
iPhoneの新作発表まとめ記事を読むようなテンションで、情報を楽しんで吸収していけるのであれば問題ないと思います。一方、IT用語が分からないとか、情報を読むのが苦痛に感じるならあまり向いていないかもしれません。
向いてないなと思ったら転職してもOK

「文系でSIerに入社したけどやっぱり向いてないな…」という場合は、転職もアリです。ただし、転職する場合は職務経歴と少なからずマッチする職種への転職が理想で、そうなるとITの職種がオススメです。IT関連の職種というと、プログラマー、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、ストレージエンジニア…等多種ありますが、文系の人にお勧めは「社内SE」です。
実際に開発するというよりも、発注する側の立場になるので、技術力よりもコミュニケーション能力を求められる職種となり、文系の方が活躍しやすい職種です。
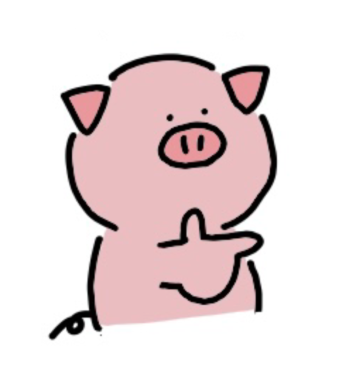
社内SEへ転職するのにおすすめの転職エージェントを下記でご紹介します!
社内SEのおすすめの転職エージェント

特に社内SEは企業における必要人員数自体が少なく、優良なホワイト企業は離職率も低いため、求人自体が他のIT職種に比べて少ない傾向にあります。そのため少なくとも2社以上に登録することをオススメします。私がおすすめする転職エージェントは下記です。
1位:マイナビIT AGENT
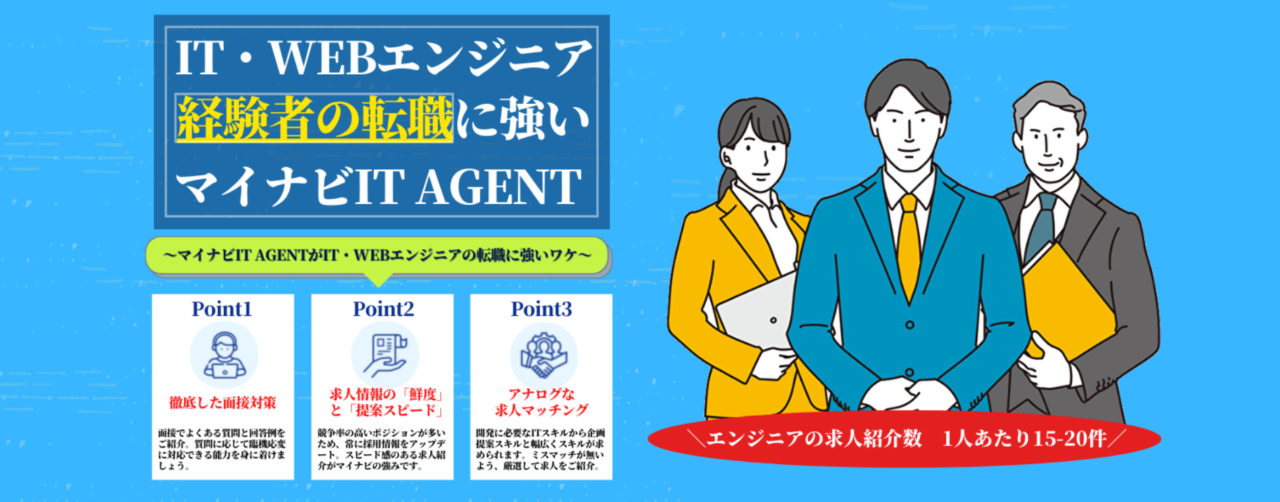
画像引用元:「マイナビITエージェント」公式サイト
マイナビIT AGENTはIT業界・業種を専門としていて、社内SEへの転職を検討するならばまずは利用を検討したいエージェントです。マイナビエージェントとの違いは、IT業界・職種を専門にしていること。社内SEの転職に詳しいアドバイザーが、職務経歴書・面接対策をサポートしてくれる点が何より心強いです。

社内SEへの転職を考えている方に一番おすすめできる転職エージェントです!実際に私も利用しています。働きながら転職をするのって、結構大変なんですよね…。マイナビIT AGENTであれば、職務経歴書・履歴書の添削、業界・企業情報の提供、志望企業への推薦など様々な点で転職をサポートをしてくれます。
2位:リクルートエージェント

画像引用元:「リクルートエージェント」公式サイト
リクルートエージェントは業界最大級の非公開求人数を保持しています。また各業界・各業種に精通したキャリアアドバイザーが、転職者に寄り添ってサポートしてくれます。社内SEは枠が少ないこともあり、特に優良企業の社内SEの求人はすぐになくなってしまうことが多いです。そのような求人は倍率が高いこともあり、複数のエージェントサイトに求人を出さなくても優良な人材を獲得できるという側面もあり、単一のエージェントにしか求人が出ない場合もあるので、複数のエージェントに登録しておくことがおすすめです。

マイナビIT AGENTにない求人を補完する目的でリクルートエージェントにも登録して併用するというのがおすすめです!個人的には上記の2社の併用が最もおすすめです。
3位:doda
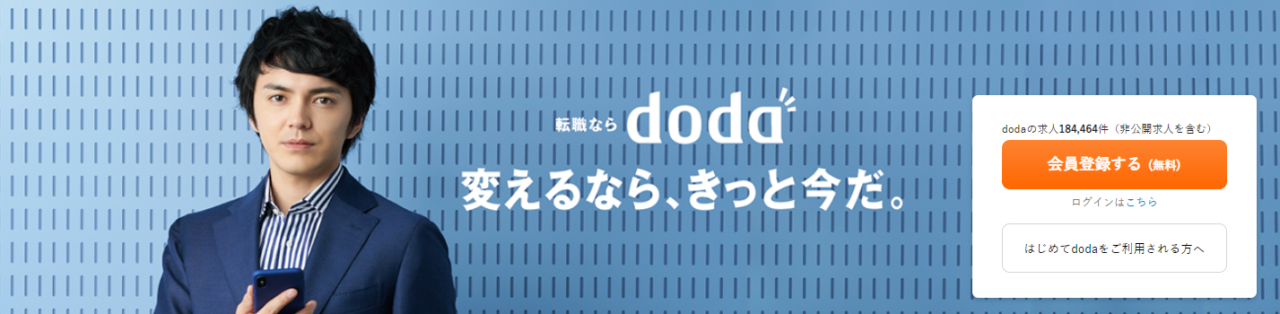
画像引用元:doda公式サイト
dodaは大手・優良企業を中心に常時豊富な求人情報を掲載している転職サイトです。IT・WEB業界に特化した専門的なアドバイザーが複数いることも特徴です。

マイナビIT AGENTにない求人を補完する目的でリクルートエージェントのほかにdoda
![]() も登録しておくとさらに網羅性が高くなり、より理想の企業の求人を見つけることができます!管理ページやアプリの使い勝手は各エージェントによって異なるので、色々と登録してみて取捨選択するのもありですね。
も登録しておくとさらに網羅性が高くなり、より理想の企業の求人を見つけることができます!管理ページやアプリの使い勝手は各エージェントによって異なるので、色々と登録してみて取捨選択するのもありですね。
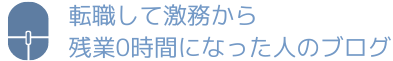
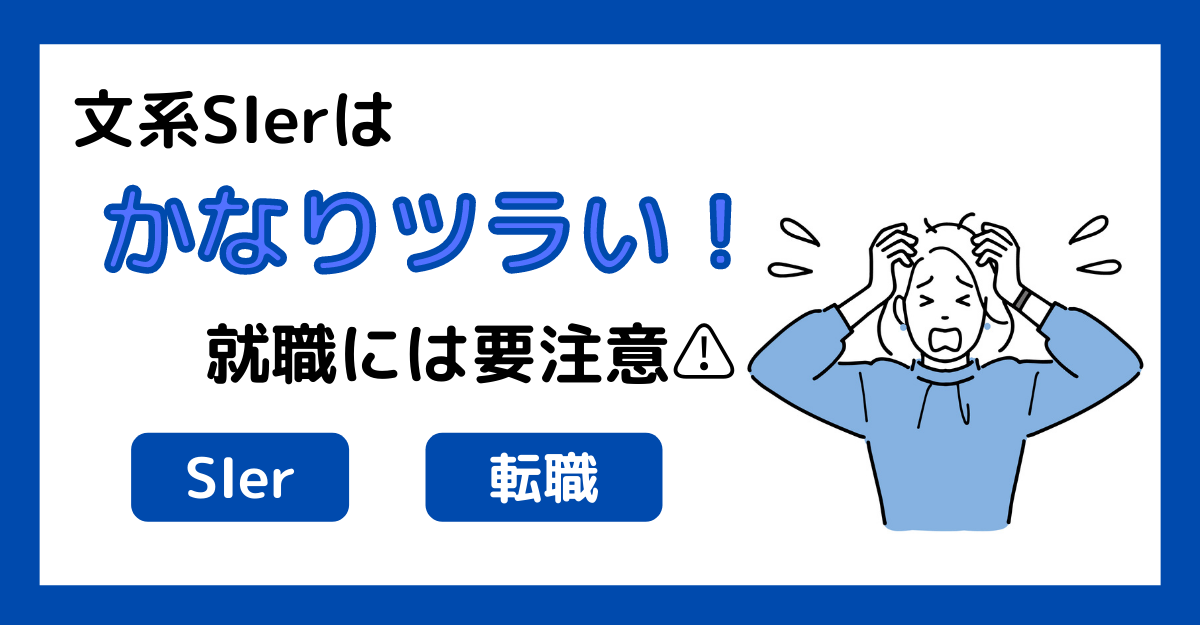
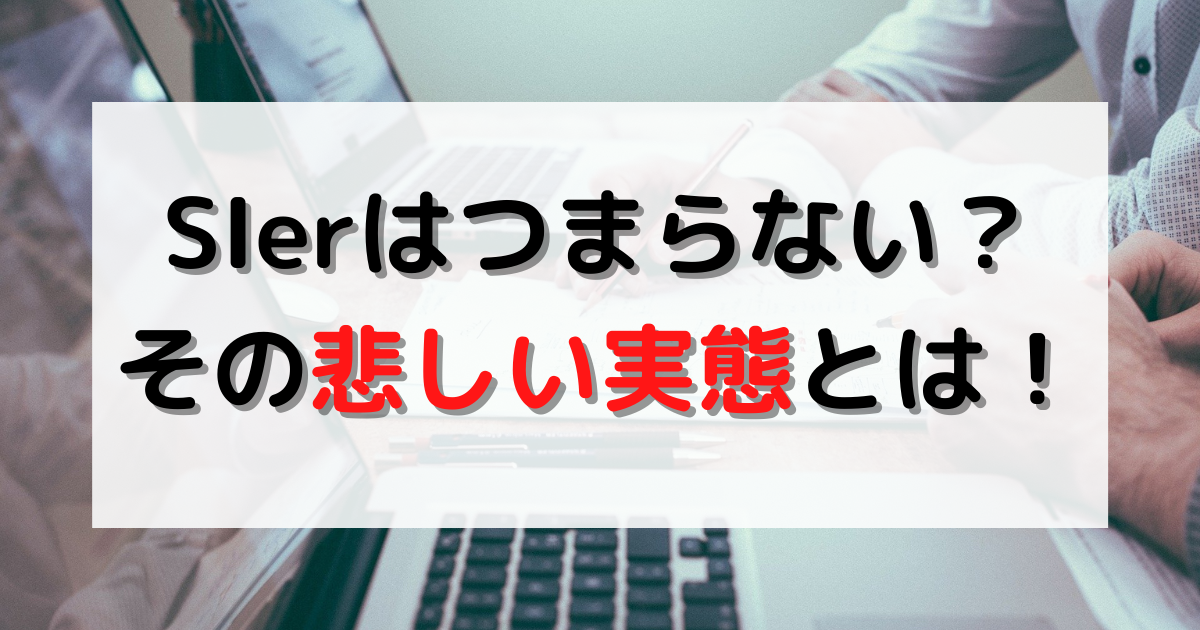
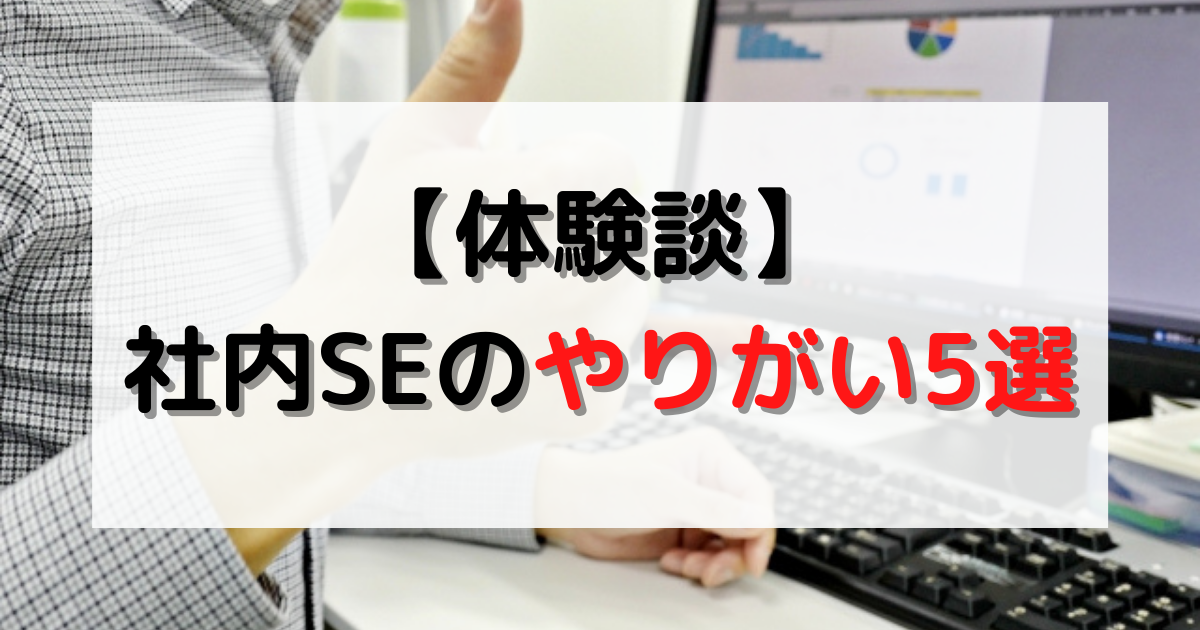
コメント